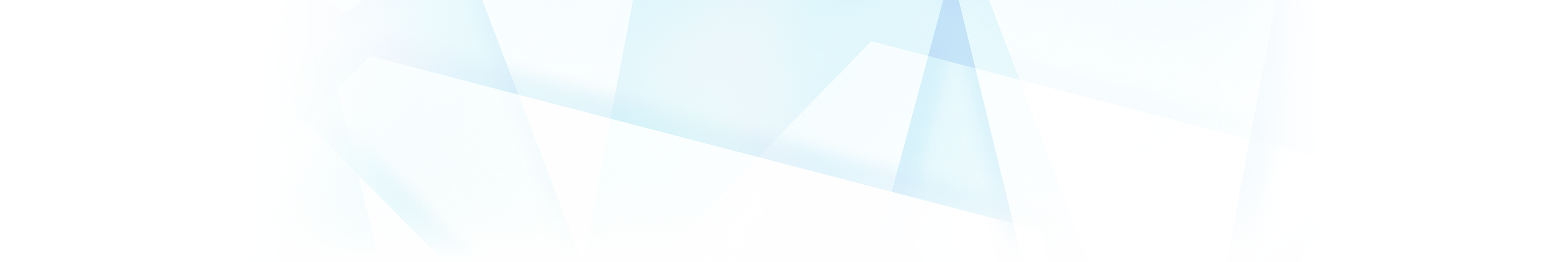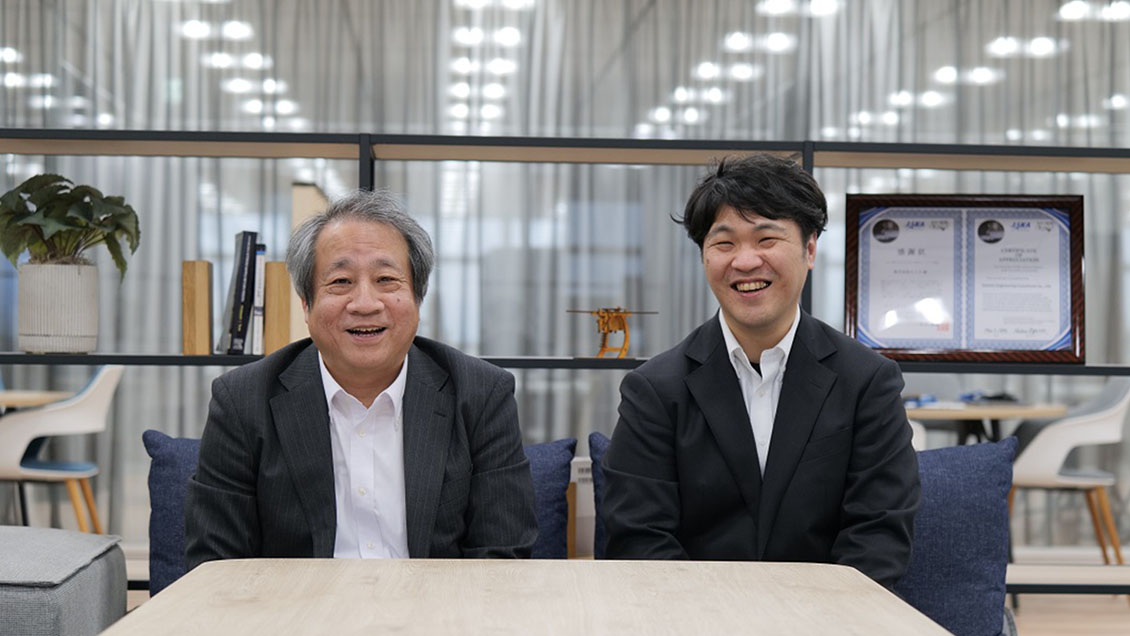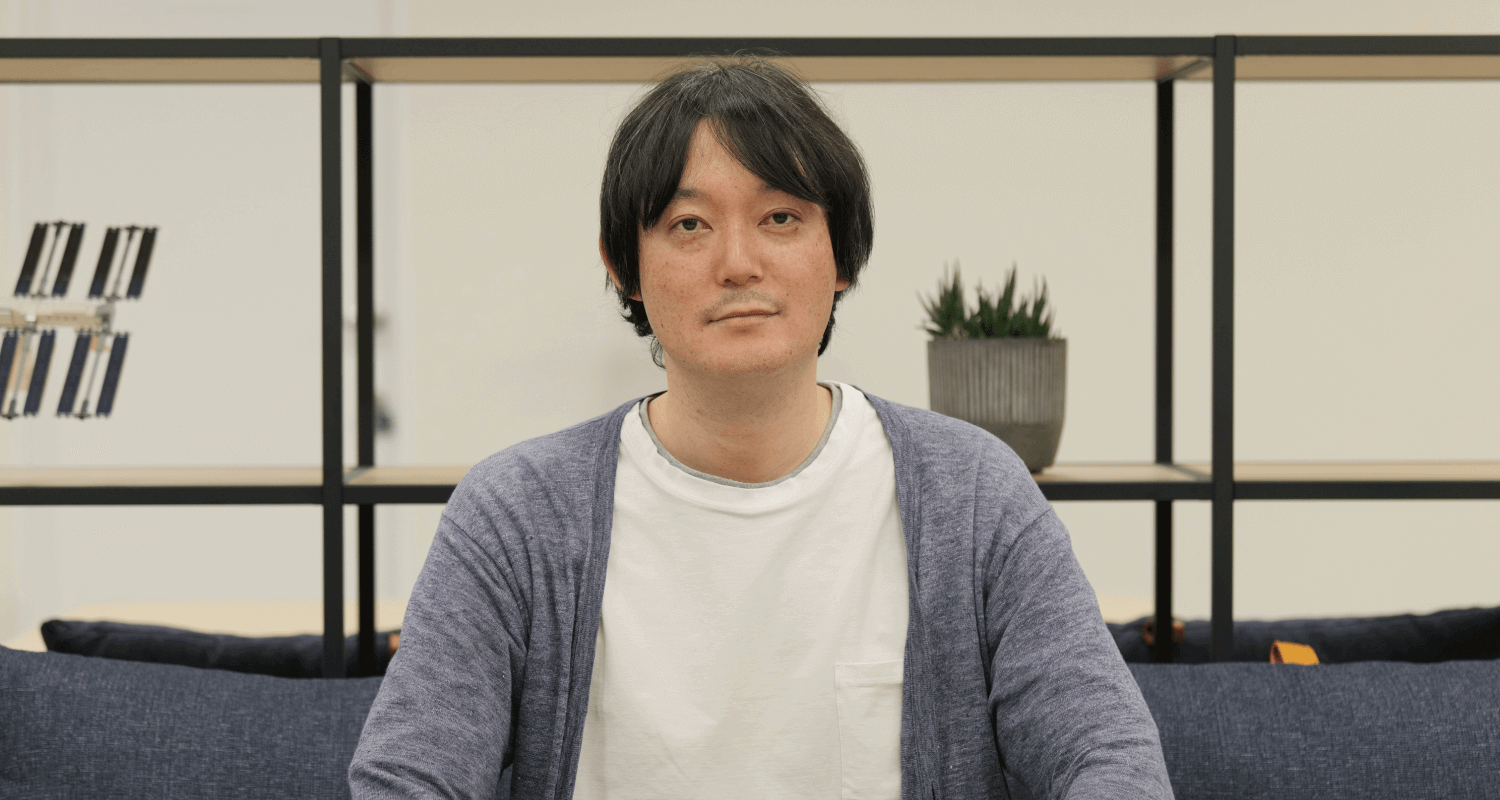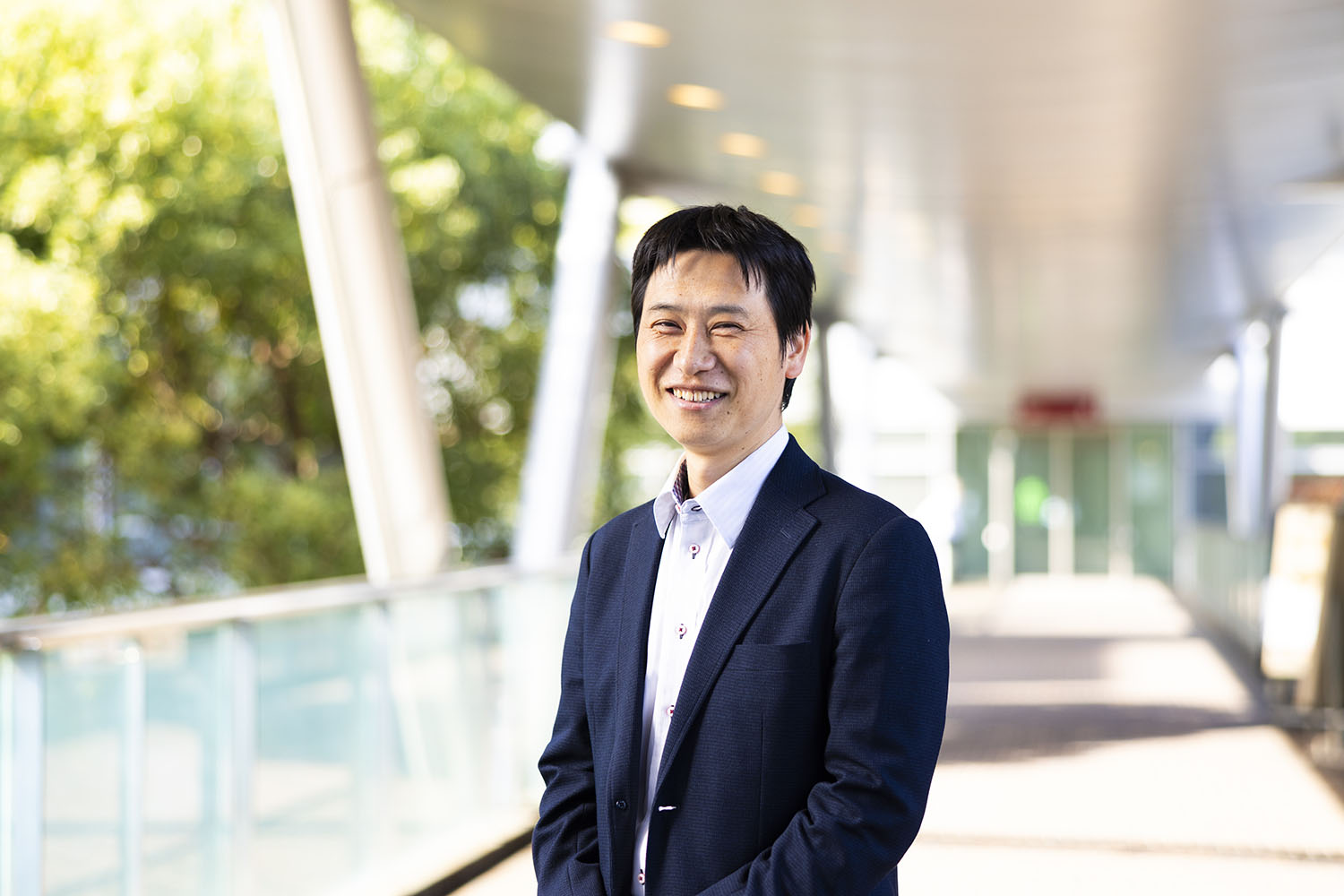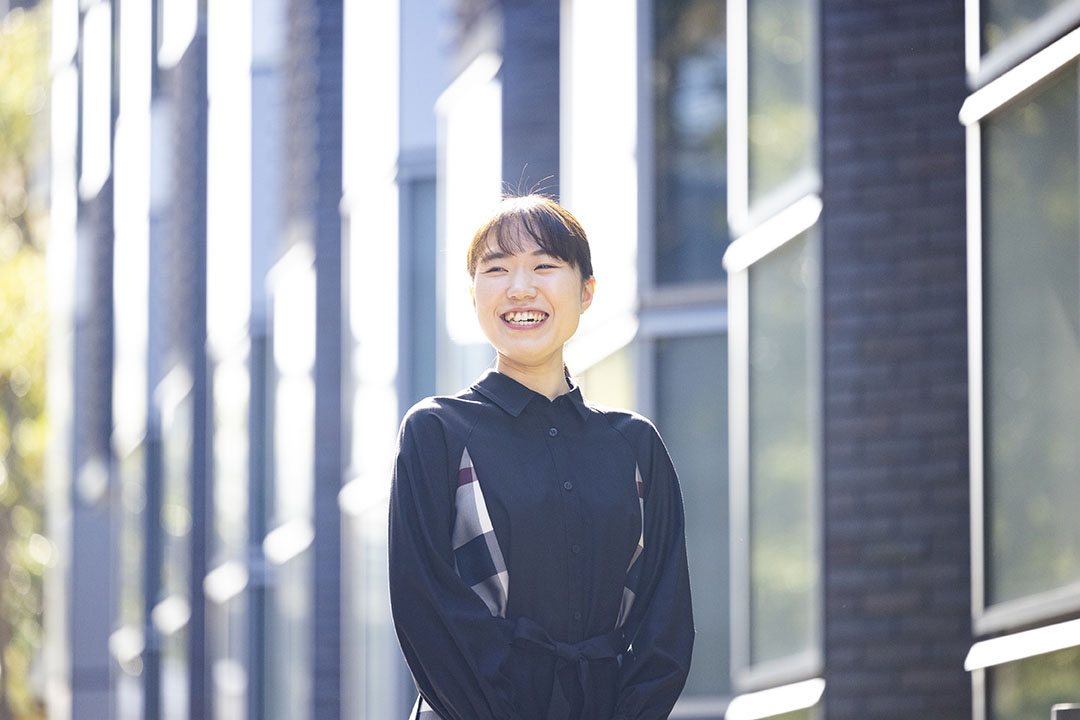JAXAが主催する国際的なロボットプログラミング競技会を支援するプロジェクトでリーダーとして活躍しているW.Y.さん。社内で軽音楽部を立ち上げるなど、オンオフともにエネルギッシュに活動しています。
学生時代は物理学を専攻していたというW.Y.さんですが、そのルーツには、いつも彼の好奇心を刺激し、新しい世界への扉を開いてくれたご家族の存在がありました。何気ない日常の「なぜ?」から始まった探究心が、どのように彼を成長につながっていったのが。その過程と、彼が感じるセックならではの文化、そして仕事への想いに迫ります。
W.Y. 開発本部第三開発ユニット プロジェクトリーダ
父の影響が大きいですね。父が電子工作好きで、高校生の頃に「こういうのは自分で作るんだよ」と教えてもらったのが始まりです。音楽もそうで、中学の卒業祝いに当時すごく欲しかった携帯ゲーム機の話をしたら、父に「そんなクリエイティビティがないものでいいの?」と言われまして…。父は若い頃からバンド活動をしていて、その足で中古楽器店に連れていかれ、ギターを買ってもらったのが楽器を始めるきっかけになりました。
そうですね。そして、その父がくれたきっかけが、大学での専門分野にも繋がっていきました。電子工作で使っていた「はんだ」が、異なる金属を混ぜると低い温度で溶けるのが不思議で、「なんでだろう?」と調べ始めたのが、大学で固体物理学を専攻するきっかけになりました。
大学の研究室では、シミュレーション結果を可視化するために、初めて本格的にプログラミングに挑戦しました。授業でプログラミングの課題を解くのが周りの人よりも速くて、「自分はプログラミングが得意なのかもしれない」と思ったんです。プログラムのエラーの原因を見つけるのも得意で、友達から頼られることもありました。その経験から、物事の仕組みを論理的に考えて課題を解決していくソフトウェアエンジニアという仕事は、自分に合っているんじゃないかと感じるようになりました。
就職活動では3つの軸を持っていました。1つ目は「早くからリーダーのような、全体を広く見る経験がしたい」ということ。そのため、まずは大企業ではないところを探していました。2つ目は「先端技術に積極的に挑戦している」こと。そして3つ目は、ベンチャーとは違い「歴史が長く、技術的なノウハウが蓄積されている」ことでした。この3つの軸で探した時に、セックがまさにぴったりだったんです。
良い意味で、想像以上でした。特に感じるのは、社員一人ひとりの人柄の良さと、コミュニケーションの活発さです。私のような若手でも、お客様対応を任される機会があり、自分の意見を言いやすい雰囲気があります。まるで「大学の研究室」のような感覚に近いかもしれません。先輩後輩とも垣根なく交流があって、それぞれが自分の専門分野や好きなことにこだわりを持って仕事に取り組んでいます。そういう環境だから、自然と新しいことに挑戦してみようという気持ちになるのかもしれませんね。
「早く決めること」を意識しています。何かを決断する場面で迷っていると、その時間がもったいないですよね。だから、いつでも的確な判断ができるように、プロジェクトの背景や状況といった情報を常にインプットしておくことを大切にしています。もし自分一人で解決できない壁にぶつかった時は、抱え込まずにすぐに周りの人に相談します。まずは情報を集めて、周りを頼る。そうやって、物事を前に進めていくようにしています。
会社のサークル活動に補助金が出る制度ができたのを知って、楽器経験の噂を聞きつけた人たちに片っ端から声をかけたんです。今では20人くらいの仲間が集まりました。部長という立場で活動を進める中で、「自分から動き出すことの大切さ」を改めて学びましたね。打ち合わせが停滞した時に「じゃあ、こうしませんか?」と一歩踏み出す勇気が、結果的にみんなにとって良い方向に進む。この経験は、日々の仕事にもすごく生きていると感じています。

「自分に高いモチベーションがあるという感覚ではないんです。」
インタビュー中、W.Y.さんは少し照れたように語りました。
しかし、彼の言葉の端々からは、目の前の課題を見つけ、それを解決すること自体を心から楽しんでいる様子が伝わってきます。
その純粋な探究心と、物事を前に進めるための行動力こそが、彼のモチベーションの源泉なのでしょう。
年次や役職に関係なく、誰もが挑戦でき、困ったときには自然と助け合える仲間がいる。
W.Y.さんのように、好奇心を原動力に新しい世界の扉を開き、仲間と共に成長していく — そんな働き方が、セックにはあります。
(取材・文/セック・広報担当)