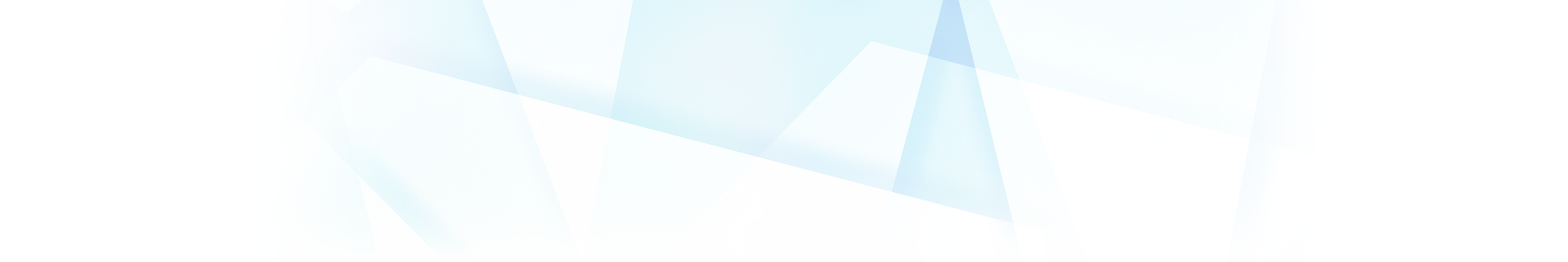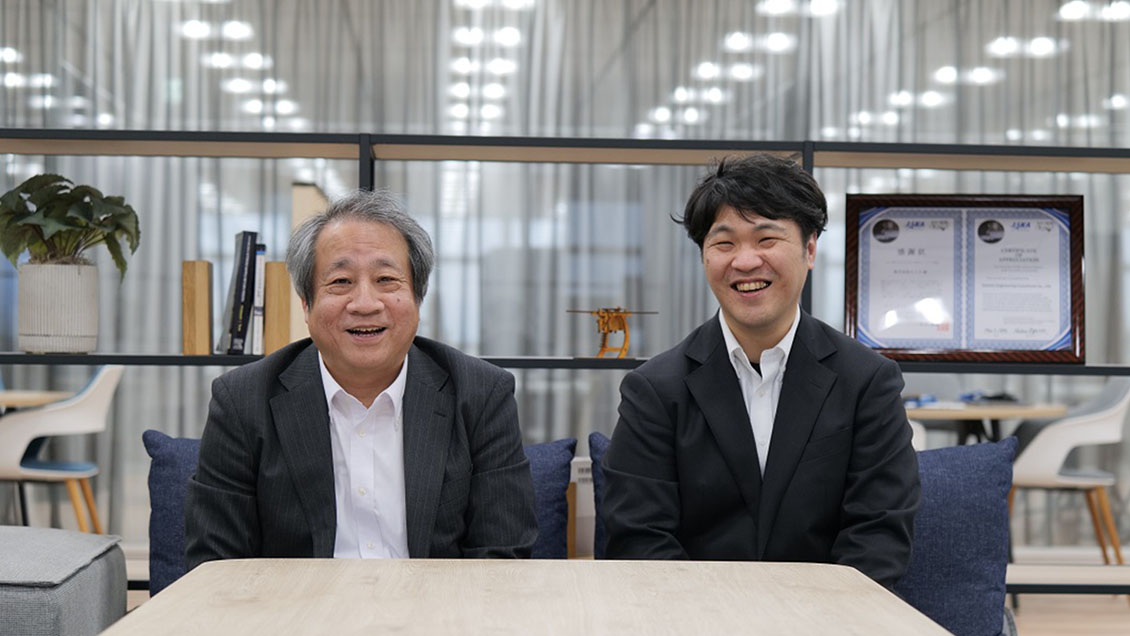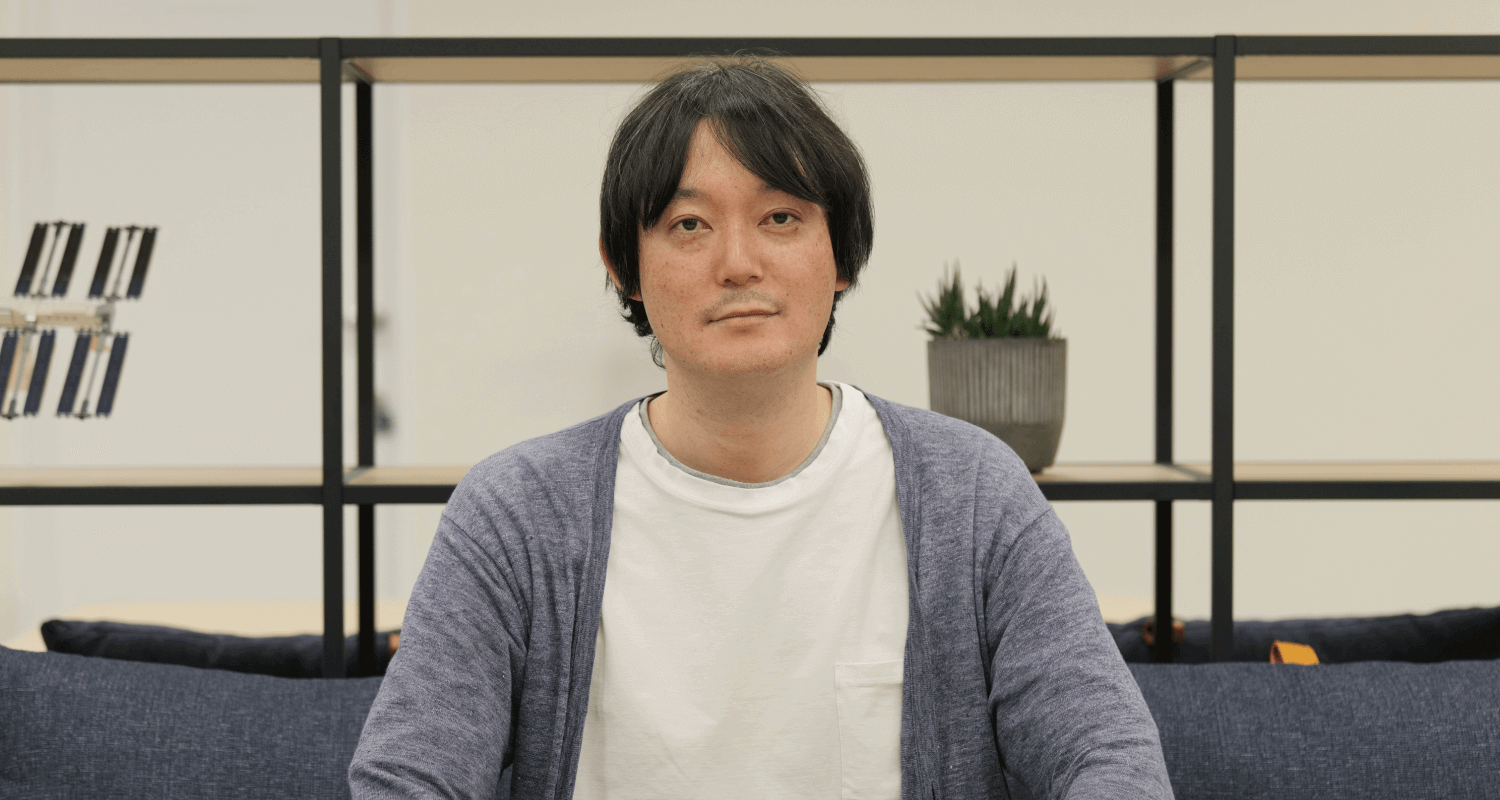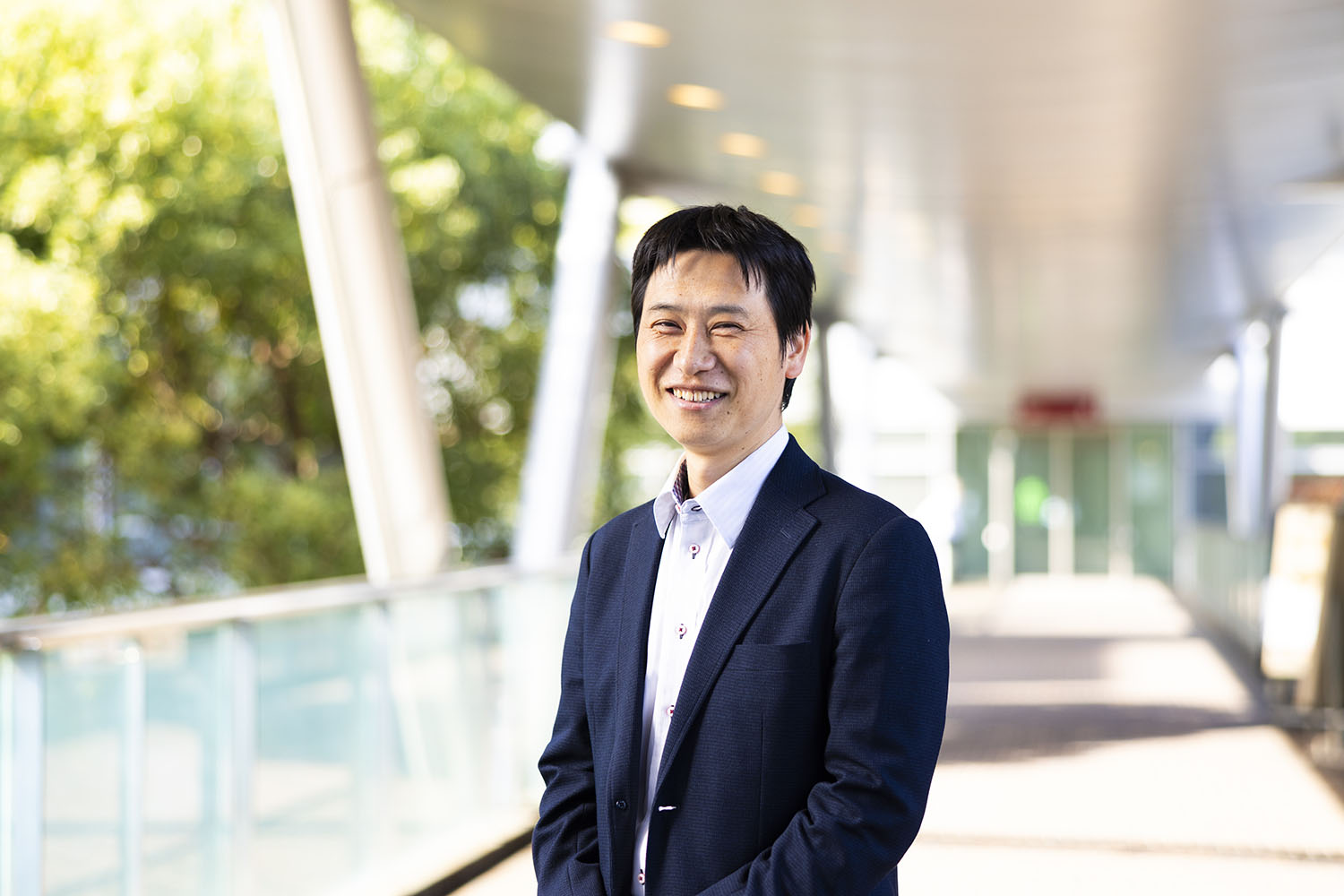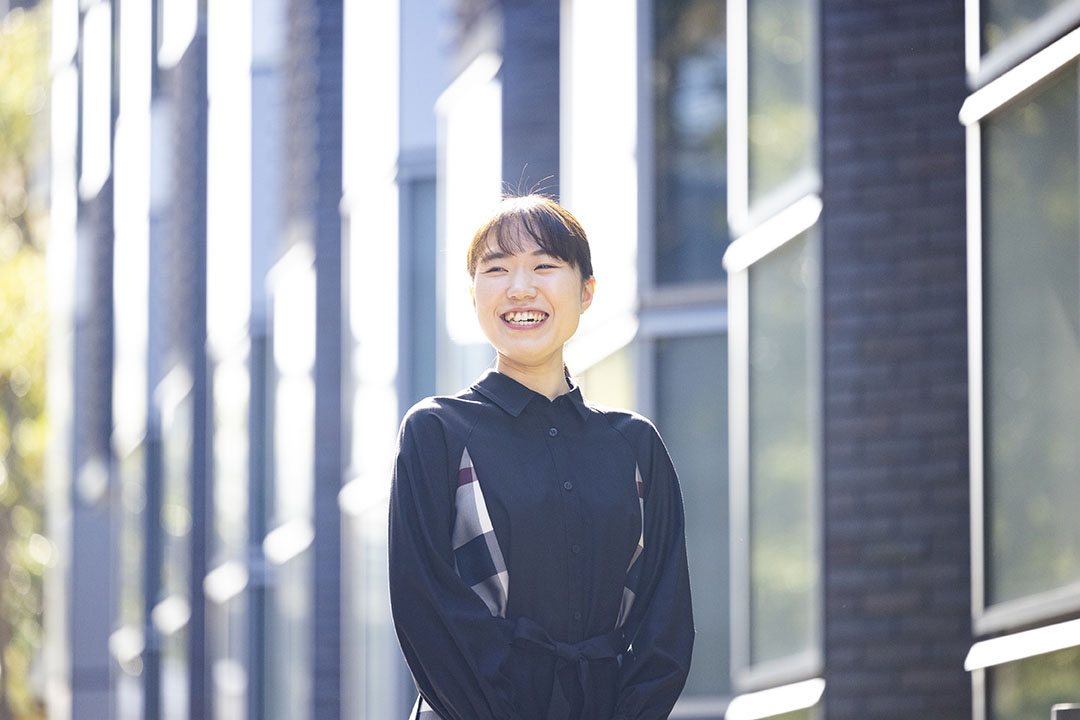セックには、品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)を軸に、新たな価値を生み出すイノベーション(Innovation)を加えた「QCD&I」というビジネスコンセプトがあります。この考え方は、お客様満足の基盤であるQCDを強化しながら、研究開発による変化先取りでイノベーションを推進し、最高のお客様満足を実現しようというもの。いわば、高い信頼性が求められるシステムの品質確保と、先端技術を活用した新しい可能性へのチャレンジを組織として両立させているといえます。
セックは管理部門と製造部門のそれぞれに、役割は異なりながらも、QCDとイノベーションをサポートする部門を配しています。今回はこの2部門の担当者に、QCDへのこだわりとイノベーションへの取組み、リスクを取りながらも成果を出す仕組みについて話を聞きました。
R.K. 開発本部開発技術室 室長
N.S. 管理本部事業推進部 部長
N.S.さん(事業推進部)
事業推進部は、管理部門に属するチームで、セックのルール作りや手順整備など、マネジメントシステム全般を統括しています。具体的には、ISO 9001(品質マネジメントシステム)やISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)といった第三者認証の維持・運用をはじめ、プロジェクト管理の仕組みや社内規程類を整え、QCD(品質・コスト・納期)を現場でしっかり守れるようサポートするのが役割ですね。
一方で、契約や購買を通じた調達機能、社内システムの整備・運用なども担っています。いわば「間接部門」として、プロジェクトが成功するための土台を整えている形です。
R.K.さん(開発技術室)
開発技術室は、製造・開発部門側の横串的な部署です。新しい技術を全社に広めたり、進行中のプロジェクトの動向をモニタリングしたりして、問題が生じる前に手を打てるように支援しています。最近では、生成AIを使ってプロジェクト報告のドキュメントを解析し、潜在的リスクを早期に発見するシステムなども構築しつつあります。
事業推進部が整備しているルールや手順を現場にどう落とし込むかは開発技術室が担いつつ、さらにAIなどで効率を上げてQCDを守りやすい仕組みを提供していきたい、という感じです。
N.S.さん
「QCD」は品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)を最適化する概念として広く知られていますが、セックではそこに「I(イノベーション)」を加えた「QCD&I」という考えを大切にしています。
ただ効率よく品質が高いものを納めるだけでなく、イノベーションを取り込んで新しい価値を創造したい。その姿勢が全社的な方針として根づいており、私たち事業推進部もプロジェクト運営の中に「QCD&I」を定着させる仕組みを整えています。
R.K.さん
「QCDをしっかり守る」だけでは差別化が難しい時代です。そこで、研究開発で新しい要素(New Element)を先回りして準備して、新しいシステム(New System)につなげることで、プラスアルファの価値を提供する。これこそがイノベーションの役割です。私たち開発技術室は、AIをはじめ、生産性を高める仕組みや情報共有の仕組みを提供して、そこから生まれる余力やアイデアをイノベーションに振り向ける仕掛けを考えています。QCDを守りながら「新しい提案」をできるようになるのが理想ですね。
R.K.さん
いちばん重要なのは、お客様の要望・要求事項を外さないこと。特に官公庁や宇宙・防衛など複雑な要件が多い分野では、誤解や見落としがあれば一気に負債が膨らみます。セックではしつこいくらいに要求事項の確認やレビューを行い、開発の初期段階で大きな齟齬を防ぐんです。また、設計をドキュメントとして残すだけでなく、プロトタイプを早めにお客様に見ていただくなど、「後戻りが少ない形」を徹底しています。リスクが顕在化すると影響が大きくなってしまうため、最初の要件定義からこだわる文化が根づいています。
N.S.さん
管理部門としては、ISO 9001(品質マネジメントシステム)の認証をはじめとする、各種マネジメントシステムをしっかり運用しています。とはいえ、セックのやり方と仕組みは「プロジェクトごとに考える余地を残す」のが特徴です。ガチガチのルールで縛るのではなく、原則を示して現場が最適な手法を選べるようにする。プロジェクトの裁量・自由度が高い一方、その分の責任も伴いますが、会社理念にある「自律自助の精神で臨む」ことを大切にしています。だからこそ、品質確保や納期遵守のルールが形骸化しにくいと思っていますね。
N.S.さん
セックは「品質を高めるほど、結果的にコスト削減や納期短縮に繋がる」という考え方を前提にしています。初期段階でしっかり要件や設計を固め、不具合を最小限に抑えることができれば、最終的に全体のコストや工期が少なくて済むわけです。
受託開発はリスク込みで受注しますから、リスクを抑え、コストを削減できれば、それは利益につながります。品質重視の成果は利益率に現れるということで、売上高営業利益率の2桁維持を目標にしています。そのために生産性や効率化をどんどん進める一方、研究開発投資もしっかり行っています。
R.K.さん
コスト(C)や納期(D)を守りつつ、イノベーション(I)を起こすには、余白(時間や予算)が必要です。その余白をどう作るかがポイント。そこで、プロジェクト管理の部分でAI解析などを導入し、早期のリスク発見や自動化を進めているんです。
実際、すべて人の手で報告や分析を行うには限界がありますから、AIにある程度委ねれば、その分新しい技術や顧客への提案を考える時間が生まれる。そこが「QCD&I」の一番難しくも面白いところだと思います。
R.K.さん
AIやロボット、IoTなど先端技術が猛烈なスピードで進化していて、ソフトウェア開発も大きく変わりつつあります。だからこそ、基礎をしっかり身に付けているセックのエンジニアの強みが生きると感じています。
「とにかく安く早く」だけを狙うのは他社もできますが、セックは「リスクを適切に抑え、品質を確保する」ことを前提にコストや納期を最適化し、さらにイノベーションをプラスする。そこが長期的な信頼に繋がるポイントではないでしょうか。
N.S.さん
管理部門としては、社内の仕組みやガバナンスを整えつつ、新技術導入を後押ししていきます。たとえば事業継続マネジメントシステム(ISO 22301)や情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001)の体制を万全にし、万が一のトラブルでもスピーディーに復旧できるようにしています。
そうした土台があるから、開発現場がチャレンジしても大きなリスクにはならない。これがQCD&Iを支える強固な基盤だと考えています。この基盤に「粘り強い組織力」と「基礎重視の技術力」を加えて、成長をしていきたいですね。
品質(Q)・コスト(C)・納期(D)を窮め、イノベーション(I)で飛躍する ―「QCD&I」はセックが掲げる独自のコンセプトであり、ただ効率化を目指すだけではない、お客様を重視する経営姿勢を示しています。
事業推進部が規程やガイドラインを整備して仕組みをつくり、開発技術室が先端技術やAIを活用して「リスクを管理し、成果を出す」プロジェクト運営をサポートする。リスクをコントロールした結果生まれた余力で研究開発や提案活動に取り組める。この好循環がセックの強みの一つと言えるでしょう。
セックが官公庁や防衛を始めとする社会基盤システムや宇宙分野など「ミッションクリティカル」な領域で成果を積み重ねてきた背景には、企業文化として根づいた品質へのこだわりと、コミュニケーションを惜しまない姿勢がありました。品質・価格・納期の最適バランスによりお客様満足と利益を両立し、高付加価値化の推進でさらなる成長を目指していきます。
(取材・文/セック・広報担当)